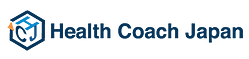2023年にICFの資格認定制度が大幅に変更になり、ACC資格を取得するための認証プログラムは、ACSTHからLEVEL1に、PCC資格を取得するための認証プログラムは、ACTPからLEVEL2に変更になりました。
これに伴い、ヘルスコーチ・ジャパンも、それまで実施していたACSTHプログラムの内容を変更し、コーチングスキル完全マスターL1コースとして開催しています。
新制度になってから7人目のACC合格者が出ましたので、インタビューを行いました。今回の合格者は内科医として仕事をされている、Gさんです。
Gさんは、最初は資格をとるつもりなどありませんでした。
コーチングに興味を持ったきっかけは、糖尿病の療養支援に使うため。昨今では糖尿病業界は、コーチングを使うことがスタンダードになりつつありますが、Gさんが、当団体の糖尿病コーチングの講座にいらした時は学会ではまだコーチングなんて・・・といった扱いでした。
なので、仕事で使えたらいいな、程度でスタートされたコーチングでしたが、本講座に以降されて学び続けるうちに、どっぷりとコーチングにはまり、成長のメジャーとして資格をとろうということになり、今回のACC取得達成となりました。
Gさんの学びの原動力になったのは、心理的安全性が保証されたコミュニティの力です。
1-インタビューからわかった重要ポイント
内科医GさんのACC取得までのロードマップ
- 糖尿病診療において患者の理解やエンパワーメントが重要だと感じ、傾聴スキルを求めて学び始めた。
- スタートは、病院で開催された糖尿病コーチングの講演。その後、ヘルスコーチ・ジャパンのチラシを手にし、興味を持って受講を決意。
- 本格的に学ぶために、糖尿病コーチングを受講後、本講座にも参加。最初は理解が難しかったが、継続するうちにコーチングの面白さに気づき、さらに深く学び始めた。
- 最初は資格取得の予定はなかったが、ICFの「ピアトゥピアコーチング」がセッション時間としてカウントされると知り、ACC取得を視野に入れた。
- スクールの仲間との継続セッションやメッセンジャーを活用し、100時間のセッションを達成。フィードバックを受けながら自己成長を実感。
- 資格取得を機に、コーチとしての活動を広げることを目指し、クライアントとの関わりを増やしていきたいと考えている。
- 2024/3/20 ACC修了認定試験合格
- 2024/12/5 ACC資格取得
糖尿病診療において患者の理解やエンパワーメントが必要だと感じコーチングに興味を持つ
糖尿病診療において患者の理解やエンパワーメントが必要と感じ、傾聴のスキルをやってみたけれども、うまくいかずどうしたものかと思っていたところ、病院で開催された糖尿病コーチングの講演を聞き、興味を持ったそうです。
最初は糖尿病コーチングだけに通っていたが本講座に編入
今は中断していますが、数年前は、年に2回京都で糖尿病コーチングを開催していました。Gさんはそこに来られ学ばれていました。そこから本講座に編入され、コーチングの世界にどっぷりはまってしまったとのことです。
安心安全の場、心理的安全性が保障された世界で話ができるっていうのが、嬉しかったそうです。医師の世界は厳しい上下関係があって、対等に心を許して話すということがないのでしょうね。
最初はACCなんて縁がないものだと思っていた
ACC資格はプロがとるものであり、自分には関係無いと思っていたけれども、ピアツーピアコーチングも実績100時間にカウントできると知って、成長のメジャーとしてACC資格取得にチャレンジ。
ACC Exam対策のために、勉強会を立ちあげ、仲間と共に学び続けられました。その勉強会は、他の仲間に引き継がれ、今も続いています。
仲間と一緒だから乗り越えられる
みんなコーチングを学ぶ仲間だし、当然学ぶ以上、コーチングマインドをみんな持ってるわけで、新しいコミュニティができた感じで、すごいそこは嬉しかったですね。とGさんは言います。
仲間の力は大きいですね。
2-インタビュー動画
3-合格後の率直な気持ち
Q:合格して今の率直なお気持ちはいかがでしょうか?
松下:Gさん合格ACCの認定試験終了試験合格おめでとうございます。改めまして、ACC認定資格取得おめでとうございます。
ありがとうございます。
松下:いかがですか?今合格という資格を手に入れたということで、率直に言うと今どんな気持ちでいらっしゃいますか?
ホッとしています。
松下:ホッとしてるんですね。本当にホッとしてるという感じ。その奥にはどんな思いがありますか?
2023年の初めに別に緻密な計画があったわけじゃないんですけど、よし2年間でACC取ろうと思ったのでなんとか間に合ったなっていうのもあるし、そこまで結構やっぱり心の重荷になってたんだなっていうのが。
松下:そうなんだそれ終わってみて気がついたことですか?
心の重荷は終わってからちょっと確認した感じですけど、確かにその前からちょっと苦しかったよねって。特に最近苦しかったっていうのがありましたね。
4-コーチングを学び始めたきっかけ
Q:コーチングを学び始めたきっかけは?
松下:Gさんがコーチングを学び始めたきっかけ、なんでコーチングを学ぶことになったんですか?
最初僕は糖尿病中心に診療してるんで、ある偉い先生とかの糖尿病ってその人を理解しないと診療うまくいかないっていう部分もあるし、いろいろエンパワーメントがいる技術もあって、中でも傾聴って大切だよとか、いろいろ書いてあるし講座とかでも聞くんですけど、実際コーチング学んで「よし傾聴やろう」とやってみてもうまくいかないんですよね。
松下:そうだったんですか。
うまくいかなくて。最終的にこっちは喋ってるという感じになる。
いくら頑張ってもうまくいかない中で途方にくれてたところに、コーチングっていうのが、そういう心情に役立つよっていう話を聞いて。それで糖尿病コーチングの大家の大石先生に病院に来ていただいて、講演をやってもらったんです。
松下:ああ、そうなんだ。
その時、最後にヘルスコーチジャパンのチラシを配っていて、とにかく藁にもすがる思いで行こうと思って行ってみて、最初正直よくわからなかった。
でも他に手もないしってことで糖尿病コーチングだけ通ってたんですけど、年に2回。今思えば、年に2回、丸1日丸2日やったとしてもそうそう物になるもんじゃないな。今ならよくわかるんですけど、ほんとその当時すごく大きいお金だと思ったんですけど、本講座も行くようにして、そこからだんだんハマっていきましたね。
松下:そうなんですね。糖尿病コーチング行ったの何年ぐらい前か覚えてます?
7、8年前になるのかな。
一度私も京都でお会いしたかなと思うんですが、そこから今まで学び続けていらっしゃるんですね。
本格的にやりだして、本講座行ってから最初の段階は、本当にやってるけどわからないなという感じで、時間が過ぎていったところがありましたけどね。
松下:そうなんですね。本講座に来て学び続けて、今があるんですけれども、その中でお仕事に活かしたいという思いがすごく伝わってきたんですが、その中で変化って何かありました?
そうですね。成長は少しできるようになってきたというのはありましたし、本講座に行き始めてしばらくしてから、糖尿病に活かすのもそうだけど、コーチングって面白いなっていう感覚が芽生えました。
松下:面白くなってきたんだ。
こっち(糖尿病コーチングよりもコーチングのほう)が面白くなってきて。
コーチングをやるっていうのが目的の上の方に来ちゃって。できれば仕事にも活かしたいぐらいに。
松下:そうなんですね。知らないうちにどっかで変わってきてたかな。面白さって何が面白いと思ったんですか?
何ですかね。
やっぱり安心安全の場、心理的安全性が保障された世界で話ができるっていうのが、非常に嬉しかったような気がします。
実社会ではそんなに機会ってほとんどないって言っていいと思うので、職場では当然、上下関係もあるし決して安心安全な場でもないしっていうことで、そう思うと実社会ってどうしても立場っていうものを背中に抱えながら会話するし、そういうのを下ろして人間同士で話しするって、そうそうないなと思う。それは貴重な機会だなって、それが楽しかったりします。
5-ACC資格を取ろうと思ったきっかけ
松下:ありがとうございます。ではその中で最初からACC目指してましたっけ?どこで取ろうという風にシフトなさったんですか?
最初はACCなんてプロになる人が取るものだし、僕には縁のないものだって、ずっと思ってました。
でやっぱり100時間ってそんなクライアントもいないし、もう無理だなと思って、まあまあそっちの世界だなっていうふうに思ってたんですけど、いつだったかICFが「ピアトゥピアコーチング」もきちんと練習じゃなくて、コーチングとして形でやれば、時間にカウントしていいんですよっていうふうに言ってくれたんで、それなら僕にもひょっとしたチャンスがあるかもしれないと思って、じゃあ一回頑張ってみようかなと思って。
松下:ピアトゥピアがOKになったというところをチャンスとして捉えた。そしてやってみようとチャレンジなされたんですね。
そうですね。あれがなかったらもうずっと諦めていたと思います。
松下:そうなんですね。そうすると一番そこに意識が向かなかったのは、今聞くとクライアントもいないし、100時間どうするんだっていうところが一番大きかったんでしょうか?
100時間も確かに重荷なんですけど、そんなに時間が取れるわけでもないし、クライアントを取ることですね。
松下:そっちなんですね。
プロを目指す人ってSNSを利用してとか、自分で将来それで仕事にしていこうと思っているので、取るためにどうするかってビジネス的な要素もすごく考えている。
松下:そうなんですね。
でも僕には今はそれ無理だと思ったので、だからとても100時間分クライアントをとるなんて絶対無理だなっていう印象がずっとあって、今もちょっとあるんですけど、そんな中で「ピアトゥピア」なら皆さんにお願いすればできるんじゃないかという、ちょっと希望みたいなものが芽生えた瞬間でしたね。
松下:今希望とおっしゃったから、なんとなく無理だと思いながらも前を向いてやっていったんですね。
そうですね。コーチング続けるなら、成長のメジャーっていうのが、持ちにくい分野だと思うんで、唯一あるのが例えばACC、PCC、MCC、大きくドーンドーンとそれに乗れるっていうのは、ある意味嬉しかったのかもしれないですね。
松下:成長のメジャーとしてってなんでしょうね?マイルストーンなんて私たち言い方しますけど。そこには向こうにはあるぞっていうのは、確かにこのICFのプログラムの中では言いますよね。
当初はそんな意識はなかったんだけど、だんだんみたいなところですね。僕あんまり明確なものはないんで、僕は知らないだけなんですけど。
6-資格取得要件の100時間はどうやって達成したのか?
松下:「ピアトゥピア」で100時間積み重ねたということなんですが、どういうふうに「ピアトゥピア」で広げて100時間積み重ねていったのか、具体的に教えていただいていいですか?
最初はスクールで親しくなった人に直接お願いして、ということをやっていたんです。
当然ICFがコーチングですので、「1回限りじゃなくて3ヶ月とかやりませんか?テーマを持ってやりましょう。」ということでお互いやってきて、
ただやっぱり数はそんなに増えないんで、最上さんも言っていましたが、メッセンジャーとか使ってやっていいよ。とかそんな話になって、そこでボーンと出したら意外とたくさん来てくれて、
そこからちょっと数が増えて、それでやっていってるっていう感じですね。仕事もしてるんで、結構自分としてはいいペースで頑張ったなと。
松下:そうなんですね。プロセスとしてはそのスクール内で仲良くなった人に声をかけ、その次にスクールのメッセンジャーで。確かにいろんな人来てますもんね。
スクール外の方とも一部やってますけど、それぐらいですかね。
松下:継続セッションとしてやったというのが、やはりコーチングで目指すっていうか、三原則の一つの継続っていうのもやったし、多分契約書も交わしていらっしゃったんですよね。
そこがきちんとICFのルール、やってほしいということを納得でやられたんだなと思います。
もう一つ、自分のペースを作ったっていうところが、苦しくならないようにっていうところなんですけど、そこを意識したのはどうしてですか?
ベースを自分で作ったっていうところでは、作ったっていうのは自然的にそうなっていった感じですけど、もっと増やそうっていう、もっと募集ボンボンかけるとかかもしれないですけど、これはもう実生活でやっている仕事もある中で、これ以上はもう無理っていう感じだったんで。
なので、今でもちょっと苦しいぐらいのペースでずっとやってきたんですけど、でもなんとかこなせるペースだったかなと思って、ちょっと苦しいけどなんとかこなせるペース。ちょっとストレッチングっていうのをやってます。
松下:そこをしっかり自分にも自分の手を伸ばした先っていうのを作ってらっしゃったんですね。100時間積み重ねの中で意識してやってきたことはなんでしょうか?
セッションの中では、やはり地道な努力というのか修行っていうのか分からないですが、その都度それぞれテーマっていうか、その時々で承認少ないよってたくさん言われた時は少しテーマに沿ってやるし、時々優等生っぽくなってるなって自分で感じたら、それをテーマにしてみたり、
多分皆さんもそうでしょうけど、一つテーマが出てくるとやって潰してテーマまでできてっていう、それを繰り返して、それが経験の中で少しずつ少しずつ。それの繰り返しのような気がします。
松下:100時間、100時間ってやるんではなく、その中で自分で気づいた課題であるとか、フィードバックをもらったことをまた自分でテーマにして、そしてそこを意識してやってっていうステップを設けてらっしゃったように聞こえましたが、それでイメージ合ってますでしょうか?それをやっていく中で自分自身に感じられたこととかあります?
自分のことについてですね。その都度都度で見ると伸びてる気がするなと思ってるんですけど、1年とかもうちょっと長いスパンで見てると、昔の何やってたんだろうなとか思ったりすると、少しずつは進歩してるんだなって、そこで感じるような感じですかね。
松下:Gさんが自分で自分の進歩を感じたっていう。最初お会いした時、結構できないところの方にすごく目がいってる傾向があったなぁと思って、そこをちゃんとできているって自分で認められているGさんは素敵と思いました。
承認で、一番今でも印象に残ってるのは、松下コーチに言われたグループコーチングを受けるか受けないかとかいう、去年はとても受けるような気になれなくて、
意見をもらうのが、フィードバックをもらうのが全部ダメ出しに思えてたんですけど、
「今年はそれが自分のためになるもんだなってに感じれるようになりました。」と発言して、
本当にその時は本気で何気なくそう言ったんですけど、「それはすごい成長だ。」ということを指摘していただいて、
あっそうだダメ出しと思ってるのがフィードバックと思えるようになってるんだと思って、こういうのは成長の承認だなと思ってすごく感動したし、
こういうフィードバックを承認するといいんだなというふうにすごく勉強になりました。
松下:そうだったんですね。言ってる本人は忘れてるかもしれませんが、でも今言ってくださったことが私に対するすごい大きな承認になってます。ありがとうございます。
本当に学び続けていく中で自分のことを振り返るとうまくいってるという時もあれば、全然ダメっていうそれを繰り返しながら私たち階段登り続けてるなっていうのを本当に感じて嬉しいですよね。嬉しいし楽しい。一緒に学び続けられてるっていうのはありますよね。
コミュニティが嬉しかったかもしれないです。
具体的に言うと、みんなコーチングを学ぶ仲間だし、当然学ぶ以上、コーチングマインドをみんな持ってるわけで、新しいコミュニティができた感じで、すごいそこは嬉しかったですね。
松下:コミュニティというところで、今年の合宿はコミュニティというのを実は軸にしてやったんですよ。仕事だけのコミュニティ・家族というコミュニティとかありますけど、
自分たちが一緒に刺激し合いながら成長できるコミュニティって重要だねという話をしてたんで、私もとても共感というか同意しています。
100時間の実績セッションは、100時間のうち75時間が有料セッションでなければなりません。Gさんは、相互コーチング(ピアツーピア)と、個人的にお願いした人とのセッション、そこからの口コミ紹介で達成されました
人によっては、社内で許可をとり、社内コーチングで達成される方もいらっしゃいます。人事部への許可が必要ですが、給料をもらってやっているコーチングになるので、有料カウントができるのです。
ただし、上司が直属の部下に行うコーチングは、実績セッションとはみなされなくなっています。この理由は、上司部下の関係性の中で行うと、コーチングで最も重要な、Partner Withができなくなるからと思われます。
7-ICF Credentialing Exam対策としてやったこと
松下:ここからちょっと試験のことについて、お話聞かせていただいてもよろしいでしょうか。今年の11月からACC用のエグザムが出ました。Gさんどちらを受けたんでしたっけ?
新しい方(ACC Exam)です。
松下:新しい方でしたか。そうするとその前から試験対策もなさってたと思うんですけれども、ちょっと試験は変わりましたけど、具体的に対策としてどういうことをやっていたか教えていただいてもよろしいですか?
ずっとクレデンシャルエグザム(PCCと同じ試験のこと、体験重視の内容で経験が少ないACCレベルの人には少しハードルが高い)のほうを受けるつもりでやっていて、先に合格された方々もいて、いろいろ情報がたくさん得られたので、それに向かって、
僕はほっとくと直前まで勉強しないだろうなっていうふうに思うので、でも定期的にきちんとやらないと勉強できない、学べないものだなと思ったので、勉強会やりませんかって言って、みんなに声をかけたら結構乗ってきてくれて、定期的に勉強会をやりました。
勉強会をやると否が応でも自分も勉強するので、勉強が続いたっていうのが一つ大きかったです。だから参加していただいている皆さんに非常に感謝しているし、乗ってきてくれてありがたかったなと思っています。
松下:一人で学ぶんじゃなくて、みんなで学ぶ。まして、その場をGさんが作ったことは素晴らしいですよね。自分のためだけじゃなくて、みんなの冒険というところではすごい良い場を作られているなと思いました。今も続けていらっしゃいますよね?
そうですね。皆様にもお役に立っていると嬉しいなと思いますし、毎回来てくれるので、来てくれるってことは評価されてるんだなって思って続けてます。
松下:今回、合格なさいましたけれども、続けていくということですか?
まだ皆さんが続けた方がいいねって感じであるならば、僕受かっちゃったら多分モチベーションどうしてもだんだん落ちてくなっていう気はするので、誰かにバトンタッチしてやっていこうかなとは思っています。
松下:継続を前提にバトンを渡すっていう考え方も軽やかというか、柔軟だなというふうに思いました。今、勉強会もあるということで、勉強学習の内容はどういう感じでやってらっしゃったんですか?
勉強会ではICFの模擬問題10問でしたっけ?
あれをみんなで解くというか、どういうコンピテンシーから来てるんだろうねとか、どうしてこれがワーストなんだろうねっていうのを意見を出し合うというか、考え方を話し合うという感じの中でそういう見方もあるよねっていうか、やっていく中でいろいろな、もちろんコーチングに対する見方でもあるし、試験対策的な見方もあるし、そういうのをいろいろやっていくっていうのが非常に役立った感じはしますね。
松下:コアコンピテンシーとその問題を結びつけて、なぜこうなんだということを話し合った。そういう勉強会だったんですね。
あとドイツのMCCの方々は、53問出してくれているので結構やりましたね。
松下:そうなんだ。みんなで学び合って、そして今Gさんは試験合格ということだったんですね。
あとヘルスコーチ・ジャパンのコアコンピテンシーの講座2種類ありますよね?受けさせていただいてあれももちろん役に立っています。
松下:そうすると、新しいエグザムはどちらかというと知識を問う問題で正解を選ぶっていう形に変わったと思うんですけど、試験が変わったとしても学びというのは活かされました?
すごく役立ったと僕は思っています。新しい試験、11月に発表になったばっかりで、まだほとんど教材も何もあまり出てないんで。
松下:そうなんですよ。受けるときどうしたらいいと思います?
どっちでもいけますよって言われたんで。ただやっぱりエグザムの方ってワースト選ぶっていうのも、なかなか僕にとってはネックで
ベストはもうだいたいこれだよねって分かるんですけど、ワーストがなんでこっちがこれより悪いの?とか、それなら新しい方を受けようかなと。新しい方は答え一つなので、そっちの方がいいかなと思って受けました。
松下:そうか。前のは、正直言って私もワーストでは、とても悩んで外しちゃったことがたくさんあります。
ヘルスコーチ・ジャパンには、受講者が自主的に立ち上げている勉強会や実践練習会が7つあります。ほとんどがピアツーピアをやっている練習会です。
Gさんは、ICF Credential Examに特化した勉強会を立ち上げて、学びを深められました。というのも、Examは、コアコンピテンシーと倫理規定を深く読み込む必要があり、合格水準まで到達するのが結構難しいからです。
しかも、Gさんが試験を受けた時期は、経験重視のICF Credential Examと、知識重視のACC Examの両方が選べる時期でした。
ICF Credential Examの情報は世界中で出回っていて、海外サイトでは対策問題なども出ていたのですが、ACC Examに関しては、まだ情報がなくて、どういう問題が出るのかすらわからない状態でした。
そんな中での合格は素晴らしいことだと思います。
8-試験を受ける前の準備
松下:ヘルスコーチジャパンの中では多分Gさんが新しい試験で合格された1番目の方だと思いますので、ここから試験について詳しく聞いていけたらと思うんですが、いろんなプロセスもあるじゃないですか?申し込んで最初選んでという。
まず試験を受ける前までに対してこういうところを意識したらいいよとか、これから試験を受ける人に対してアドバイスというか、Gさんの考えたことがあったら教えていただいていいですか?
試験受ける前のまず申し込みで、L1プログラム(ACCがとれるコーチングスキル完全マスターL1コースのこと)を受けていると、非常に助かりました。
あのプログラムでは必要な情報がすでに揃っているので、提出物をジャンプしてペタンと貼るだけで済むんです。
松下:あれはすごく助かるなぁと思いますね。
あれはすごくありがたいなと思いますね。
あと高橋洋さんと高橋美佐コーチの動画ですね。プロセスはすごくありがたいっていうか、あれを見ながら僕もやったのであれは助かります。
だから、あれに沿ってやるのがいいのかなと思うけど、一つだけ思ったのは、ヘルスコーチジャパン、受験のためのガイドみたいなのがずっとあるじゃないですか。高橋洋さんのビデオって最後の方なんですよね。
松下:そうなんですね。
後ろの方に出てきて、それまでで実はもう昔の話なので、あんまりもう役に立たないのがたくさんあって、高橋洋さんの動画で、初めてこれだこれだっていう感じになるので、一発でそこに行けるようにして欲しいなという要望があります。
松下:はい、承知しました。じゃあそれは伝えておきますね。ありがとうございます。試験の当日って会場とか行くと多分指示があるんだと思いますが、何か気をつけた方がいいことってあります?
当日はもう体調管理に尽きるのかなっていう風に思います。
90分で休みとって30分なんですけど、途中で席を立つと時間をロスするので、体調を万全にして臨むことが大切だと思いました。
脱水にならないよう水分を摂る一方で、飲み過ぎにも注意が必要ですね。
また、しっかり睡眠を取ることも大事だと思います。
あと実際の受験のためのチュートリアルっていうのはICFが出しているので、あれは見といた方がいいなと思いました。
松下:これはICFのインターナショナルの方ですよね?
そうですね。本部の方のホームページにあります。
チュートリアルがあるんで、その時の画面が見れるので、それで例えばもっと見直したい、旗を押すとかいろいろ説明があるんで、当日のが出てくるんですけど、試験前にそれを読んでると、正直余裕ないなと。
あらかじめ、それはきちっと読んでおいて頭で「こういうふうな試験なんだなー」っていうのを持っておいたほうがいいと思いました。
松下:事前チュートリアルを見て、全体的な流れであるとか、やり方ですね。ありがとうございます。日本で受験の場合、時間は90分プラス30分で120分になりますが、余裕はありましたか?
ありました。
クレデンシャルの方のICFの模擬とか見ると状況説明するので長く感じますが、それが短いんですよ。
1点だけ聞いてくる感じなので、読む時間は十分あるなと思いました。時間的にはそんなに負担ではなかったです。
松下:120分あればokだったっていうことですね?
そうですね。僕は納得するのにちょっと時間がかかるほうなので、それでも時間が余って見直す時間もあったので、時間的には多分大丈夫かなと思います。
松下:時間的には焦る必要ない感じですかね。焦らなくていいそうですよ、皆さん。あと内容についてはどういう印象がありました?
多分、倫理規定とコアコンピテンシーが網羅されてたと思うんですが、倫理規定に関するものが結構出ました。コアコンも当然出る。
コアバリューについてはもちろんベースにあるんでしょうけど、聞く質問はなかったなっていう印象です。
松下:そうなんですね。
コアバリュー4つなので、多分3つ正しいの選んで、1つだけどれが違うのって聞いてくるだろうなと思って、4つ覚えたんですけど、そこは出なかったです。ちょっと山が外れたっていう感じですかね。
いくつかパターンがあるかもわかりませんが、倫理規定が結構出たっていうところは、やっぱり守秘義務とか利益相反に関しては何度か出てきましたね。
松下:そうなんですね。
意外とその他の最初の段階で倫理的であろうとすれば、必ず問題にぶち当たりますよ。前書きのところですかね、ああいうのに関しても出るし。
松下:そうなんだ。
倫理規定破ったらどうなるとか最後に書いてあるのも、ちょっと聞かれたりするんで。倫理規定、結構ヘルスコーチジャパンでもやってますけれど、割とコンピテンシーの方に行きがちなので。
松下:なるほど。倫理規定もしっかり押さえておく必要がありそうですね。
インタビュー内で話しているチュートリアルは、下記リンクの下の方にあります。
https://www.pearsonvue.com/us/en/icf.html
ヘルスコーチ・ジャパンには、ICFジャパンが認定している、CODE&CCアンバサダー資格を持つコーチが3名もいます。(まだ全国に10名ほどしかいない)
なので、ICF Credentialing Examで出題される、コアコンピテンシー、倫理規定、PCCマーカーを深く学ぶことができるコースが、たくさんあります。
いわいださんは全部学ばれたのですが、その中でも特に、ACCをすでに持っている人が学ぶ、PCCマーカーブートキャンプ実践会が役にたったと仰っています。
PCCマーカーブートキャンプ実践会についての詳しい情報は下記をご覧下さい
倫理規定のケーススタディを学ぶコースは下記です。これもPCC取得を目指している人用のコースです。
コアコンピテンシーの基本を学ぶのは下記となります
ヘルスコーチ・ジャパンには、他にも、完全に自宅での自習学習だけで学べる倫理のコースがあって、更新単位が必要なACC・PCC・MCCのコーチたちに喜ばれています
更新用コース一覧(全てに自習型倫理3単位がついています)
9-ヘルスコーチ・ジャパンのプログラムの良かったところ
松下:ヘルスコーチ・ジャパン以外の講座も受けられたのでしょうか?
ヘルスコーチジャパンの中でも倫理規定っていう形でありますけど、学びの場っていう講座がまたあって、それを受けたんで良かったなと思ってます。
松下:そうなんですね。そこは別の講座で時間とお金を自分に対して投資したっていう感じですか?
そうですね。試験ということで、そこではコアコンの方も受けたんですけど、やっぱり今年ヘルスコーチジャパンの方でコアコンの講座取ってなかったんですよ。取っていたら受けなかったかもしれないですけど、取ってなかったので、これ受けておいたほうがいいなと思って、そのコアコンの講座とインビキティブ講座を受けたんで助かりましたね。
松下:なるほど。L1プログラムだけじゃなく、自分からも取りに行ったんですね。ありがとうございます。これから受ける人に対して、みんなで学ぶっていうのと、倫理規定コアコンを自分でも取りに行くってありましたけど、他に何かありますか?
僕はちょっと情報不足だったんですけど、やっぱりICFのホームページにはいろいろな情報が出てるらしくて、試験終わってからもいろいろとここにこんなの書いてありますよって教えてくれる方もいるので、後で見てみたら書いてあるわと思って。
松下:あそこもいろんな情報があると思いますが、探しにくかったりしません?
探しにくいです。あと英語なので、もちろんGoogle翻訳すればいいのですが、足が遠のくっていう感じはありますね。そこも意識して自分から情報を取りに行くっていうのもあったらいいのかなって。
ACC資格の新規申請は、ICFのページから英語で行わなければなりません。ここは日本人にとってハードルが高いところなので、ヘルスコーチ・ジャパンでは、実際の申請画面を録画して、あらかじめご覧になれるように用意しています。
このサービスは、受講者の方に大変好評で、これがあったから、安心して申請できた、これがなかったら申請時点で心が折れていたかもしれないと、仰います。
他にも、契約書の雛形、会社に申請するときの書類、その他、資格取得時に必要な情報を、ひとつのプロダクト内に収めて、受講者の方提供しています。
会場は全国にあり、試験の運営は、ピアソンVUEというところがやっています。ここは、ICFの試験だけでなく、マイクロソフトやIBMなどの試験も行っているので、隣の席の人は、違う試験を受けていたというわけです。
10-ACC資格を今度どのように活かしていきたいか?
松下:では、未来のことを教えてください。ACCを取得したGさんですが、これからコーチングに対してどう向き合っていきたいと思いますか?
まだ正直あんまり考えてないんですけど、でもせっかく資格をいただいたので、ICFが認めてくれたということなので、わずかながらコーチとして少しずつ活動の幅を広げていきたいと思っています。
ある意味コーチとしてのスタートみたいな感じで、今までは練習のような感覚もありましたが、これからは本格的に取り組んでいけたらなというふうに思っていますし、なんとかチャンスをゲットしたいなというふうには思っています。
松下:ゲットしたいというのは何を?クライアント取ってということですか?
こういう方面を広げて、他でも何かないかというのはアンテナを立てて、自分でもそれならできそうだというのを探していきたいなと思っています。
松下:いいですね。Gさんがそういうふうにおっしゃってくだされて、すごく心強いなと思います。
何でかというと、プロコーチで言うともちろん必要だと思うんです。けれどもコーチングを自分の仕事を持ちながら広めていく、そこにプラスしていって広めていっていただけると、もっと社会に認知されるし広まっていくんじゃないかなっていう期待が私はあるんですね。
そしてやっぱりICFの目指している、世界をコーチングが当たり前の世界にしていくというところで、Gさんのドクターであるっていう、そこにプラスしてぜひぜひ広めていって、波紋を広げていただきたいなというところが私の希望でもありますし、期待もしております。
ありがとうございます。
松下:今コーチとしてのスタートっていうところで、ドライバーズライセンスをとって、さあ今から路上だみたいなね。そんな感じ確かにありますね。
もう自分の好きなとこ行けるし、ルートも決められるし、行き先も決められるし。Gさんのこれからのライセンスを持ってのコーチングドライブをぜひ楽しんでいただきたいなと思いました。
ありがとうございます。
11-これから資格取得にチャレンジする人への応援メッセージ
松下:では最後に、これからACC取得にチャレンジする人、ヘルスコーチジャパンにもいらっしゃいますし、そこを視野に入れて、またコーチングを学び始めようかなと思っている人もいらっしゃると思いますので、その方たちに向けてメッセージをお願いしてよろしいですか?
頑張っていきましょうっていうことにはなるんですけど、コーチングされてない方に関しては、ちょっといっぺん覗いてみてねっていうのはありますし、
もちろんされている方はACC取ろうと思っている方も多いと思うし、多分いろいろな状況において、困難な状況におられる方もたくさんいるんじゃないのかなと思うんですけど、
一方でプロになる人たちは本当に早いペースでポンポンポンポーンと進んで、能力に関しても、時間に関しても進んでいく。
そういうのを見るとはぁーと思っちゃうような時も確かにありましたし、あるんじゃないかなと思うんですけども、自分のペースで進んでいってくださいというようなメッセージですかね。
自分のペースでやっていっていいんじゃないのかなと思ってるんで、いろいろ立場って苦しいけども少しずつでもいいんで進んでいかれることをお勧めするというのか願ってるっていうのが僕のメッセージになります。
松下:ありがとうございます。そうやって進んできたGさんだからこそ、心からおっしゃってるのが伝わってきました。
学ぶ中でもいろいろ揺れたりしたこと私もあったなぁ、誰かと比べてとかってありましたけれども、今ここに来たら、まあこれでOKみたいなね、ところも感じられた。それがその時のベストだったのかなぁ、なんて、
今私もちょっとGさんの言葉を聞きながら考えました。
本当に率直にいろんなことを話してくださって、自分の経験から次にステップアップする人たちへのメッセージも本当に心に届いたなぁと私は思っています。それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
13-プロフィール
Gさん(内科医)
- 仕事は内科勤務医です。
- 仕事に役立てようと思い、HCJ の糖尿病コーチングを受講し、コーチングにはまりました。
- 年 1 回程度、次女と東京ディズニーリゾートに出かけるのを楽しみにしております。
- “あまりん”, “太陽のタマゴ”, “ブラックビート”, “新甘泉”, “南水”, “冬恋はるか”等、美味しいフルーツも好きです
松下由樹

コミュニケーション リアン代表
石川県小松市出身
- ヘルスコーチ・ジャパン クラスコーチ/メンターコーチ
- パーソナルコーチ(仕事・プライベートを包括したライフコーチング)
- 研修講師(人材育成・マネジメント・ストレングスファインダーなど)
2010年に客室乗務員として勤務した日本航空を退職。経験を通して、無意識でのコミュニケーションの取り方が関係性に大きな影響を及ぼし、個人、チーム、そして組織のパフォーマンス力、成果・結果が大きく変わることを実感する
どんな時も私たちひとり一人が生き生きと、前を向いて生きていけるようになれたらい
いと、セルフマネジメント、コーチング、ストレングスファインダー等を学ぶ。
コーチングを通して、ひとりからチームへ、チームから組織へ、組織から社会へと、
「元気・やる気・勇気」と「実現可能な未来の可能性」がどんどん広がっていくことを
目指し、2012年にコミュニケーション リアンを設立。
現在はパーソナルでのコーチング、メンターコーチング、また組織外コーチ/講師として、コーチングベースのマネジメント、リーダーシップ、部下育成等の人財育成研修を展開している。
【所有資格】
国際コーチング連盟(ICF)認定プロフェッショナルコーチ(PCC)
NPO法人ヘルスコーチ・ジャパン認定 メンタルコーチ/ヘルスコーチ
国際コーチング連盟日本支部(ICFJ)倫理規定&コアコンピテンシー・アンバサダー
米国ギャラップ社認定ストレングスコーチ