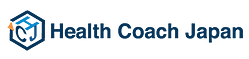2023年にICFの資格認定制度が大幅に変更になり、ACC資格を取得するための認証プログラムは、ACSTHからLEVEL1に、PCC資格を取得するための認証プログラムは、ACTPからLEVEL2に変更になりました。
これに伴い、ヘルスコーチ・ジャパンも、それまで実施していたACSTHプログラムの内容を変更し、コーチングスキル完全マスターL1コースとして開催しています。
2024年10月に、新制度になってから15人目のACC合格者が出ましたので、インタビューを行いました。今回の合格者は鈴木輝子さん(研修講師&コンサルタント)です。
研修講師やコンサルタントとして多忙な日々を送りながらも、常に自己研鑽を続ける鈴木さん。その原動力の裏には、海外での仕事で感じた「女性だから」という壁と、若き女性コーチの活躍を目の当たりにした衝撃的な体験がありました。
「クライアントと対等な立場で、無限の可能性を引き出せる」そんなコーチングの魅力に惹かれ、学びの道を歩み始めます。
学びを深める中で、スキルとしてだけでなく、ご自身のコンサルティングや研修のあり方そのものにコーチングの考え方を取り入れ、大きな変化を実感されていました。
そして、これまで学んできたことへの「けじめ」と、プロとしての誇りを胸に、ACC資格取得を決意されます。それは、ご自身の中で長年の「未完了」に終止符を打つための、大きな一歩でした。
今回のインタビューでは、多忙な仕事と両立しながら100時間の実績を積んだ具体的な方法から、試験制度の変更に柔軟に対応した学習のコツ、そして資格取得を経て得られたプロとしての意識の変化まで、赤裸々に語っていただきました。これから資格取得を目指す方にとって、多くのヒントと勇気が得られる内容となっています。
それでは、鈴木さんのお話をじっくりお聞きしていきましょう。
1-インタビューからわかった重要ポイント
鈴木輝子さんのACC取得までのロードマップ
- 学習のきっかけ: 海外在住時、若手女性が有名企業の社長のコーチを務める姿に感銘を受け、コーチという職業の対等性や将来性に強く惹かれ、帰国後に学習を開始。
- 学習の転機: 生涯現役でいるために、自分を磨き続けられる環境を求める中で、仲間と切磋琢磨できるコーチングの学習コミュニティに価値を見出す。
- 実績構築の方法: 本業である研修講師の経験を活かし、研修後のフォローアップとして受講者にコーチングを提案。通常より価格を抑えることで企業からの承諾を得やすくし、効率的に100時間の実績を達成。
- 試験対策:
- ICF公式ページの模擬試験や、ドイツの「ソリューションアカデミー」の無料シミュレーターを活用して問題形式に慣れる。
- ヘルスコーチ・ジャパンの講座で仲間と倫理規定について討議し、自身の仕事に引きつけて考えることで理解を深める。
- 合格: 3月31日にACC資格を取得。「未完了だったことが完了し、すっきりした」という気持ちで新たなスタートを切る。
- 合格後の展望: 資格取得で得た自信と倫理規定への深い理解を基に、日本の企業にもICFコーチングの価値を広め、後進の学習者を応援していきたいと考えている。
- 2024/7/31 ACC修了認定試験合格
- 2025/3/31 ACC資格取得
本業がコーチング実績に変わる!研修後のフォローアップ活用術
研修講師の仕事を持つ鈴木さん。コーチングは実践が不可欠と考え、研修後のフォローアップとして参加者に有料でのコーチングを積極的に提案しました。価格を工夫することで企業側の合意も得やすく、本業の流れの中で効率的に100時間の実績を構築。自分の仕事とコーチングを結びつけ、Win-Winの関係で実績に変えるこの方法は、特に企業で働く学習者にとって大きなヒントとなるでしょう。
多忙でも大丈夫!ICF試験の柔軟なリスケジュール制度を賢く利用
仕事や介護など、多忙な日々の中で資格取得を目指す人にとって、試験日程の確保は大きな課題です。鈴木さんは、やむを得ない事情で試験日を10回近く変更しましたが、ICFのシステムはオンラインでスムーズに対応してくれました。
試験日の48時間前までなら変更可能という柔軟な制度を有効活用することで、自分のペースを崩さずに合格を掴むことができます。諦める前に、まずは制度を賢く利用することが重要です。
独学の壁を越える!「仲間との対話」が倫理規定の理解を深める鍵
一人で読み解くのが難しいICFの倫理規定やコア・コンピテンシー。鈴木さんは、学習プログラムの中で仲間と討議を重ねることが、理解を深める上で非常に効果的だったと語ります。特に、利益相反など自身の仕事に引きつけて考えることで、知識が具体的で実践的なものになりました。仲間と学び合う環境が、複雑な概念を腑に落とし、自信を持って試験に臨む力となったのです。
2-インタビュー動画
3-合格後の率直な気持ち
Q:合格して今の率直なお気持ちはいかがでしょうか?
原林:鈴木さん、この度はACC合格おめでとうございます。
ありがとうございます。
原林:合格を手にされたのはいつでしたか?
3月31日ですね。
原林:そうですか。今日はACC合格までの道のりだったり、当日の試験のことでしたり、いろいろと伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原林:早速ですが、合格して今の率直なお気持ちはいかがですか?
そうですね。何かほっとしたっていうか、ずっと未完了でできてないっていうか、終わらせていないことが、ズルズルしていたのでそれが決着がついたっていうか、完了したっていうことで、すっきりしています。
原林:そうですか。未完了が完了したっていうとこなんですね。
はい。
4-コーチングを学び始めたきっかけ
Q:コーチングを学び始めたきっかけは?
原林:鈴木さんはもうコーチとしてもずいぶん長く学んでこられてる方なんですけれども、そもそもコーチングを学ぼうって思われたきっかけは何だったんですか?
コーチという存在を知ったのは、私が海外で仕事をしてたときなんですが、そのときに多分ネットかテレビかどちらかなんですが、世界的に有名なGっていう会社の社長さんのコーチを27歳の若い女性がしてたっていうインタビューみたいなのが出ていてびっくりして、すごい可能性とかチャンスがあるんだなと思って、ぜひやってみたいなと思っていました。 そこで帰国後すぐ始めました。
原林:その当時っていうのは、まだコーチっていう職業はあんまり知られていないような感じだったんですか?
そうですね。日産のゴーンさんが社長だったときに、コーチングを役職者にやらせるみたいなことで、少しずつ盛り上がってる感じはありました。
原林:その中で若い女性がエグゼクティブのコーチをしているっていうところに、何かびびっとこられたそんな感じなんですね。
そうですね。私の場合はいろいろな仕事をしてきたんですけど、結構壁にぶち当たるときに女性だからっていうような、ハンディを少し感じていたので、対等であるっていうコーチの考え方、クライアントとコーチ自体はイーブンというか、上下もなく対等であり、いろいろな方と業種とか自分のキャリアと関係なく、いろんな方とお目にかかってお話ができるってことにとても興味を感じました。
可能性っていうか、未来的っていうか、そういう差別とか区別がない職業なんだなっていうのがすごく魅力的でした。
原林:まさにICFの唱えるところのコアバリューだったり、そこに通じるような世界が広がってたんですね。その映像を目にされたときに。
そうですね。びびっときました。
原林:そうでしたか。そんな中でコーチングを帰国されてからずっと学び続けて、お仕事だったり、生活の中で学び続けるってことはどうでしたか?
そうですね。自分としてはやはり活躍するとか成長するっていうことが好きなので、今は生涯現役でいたいっていう、ボケ防止じゃないのって人に冷やかさせることもありますが。そういうふうに自分をいつも切磋琢磨できる場というのが、コーチングにはあるなと感じています。
原林:切磋琢磨できる場。ずっと成長をし続けたいとか、自分を磨き続けたいっていうような、お気持ちが伝わってくる感じがします。
あと仲間の人たちもやっぱりお互いをブラッシュアップするっていうか、コーチ同士もあるしクライアントもそうかもしれないんですけど、そういう関係性が整ってる感じが私にはしています。
原林:そこはコーチングの魅力であるところですよね。
はい、そうだと思います。
原林:ありがとうございます。お仕事は研修講師をなさったり、コンサルタントをなさったりって伺ってるんですけど、その中にコーチングってのはどんなふうに生きていましたか?
最初のときはなかなかそういうことにあれこれっていうのは気が付かなかったんですけど、今ではあらゆるところにコーチング的な要素とか関わり方、考え方がすごく使われているし、使われてきているなと思いますし、自分でもそれを積極的に活用しているなというふうに感じています。
原林:コーチングを学ぶ前と学んでから、ご自身の中でここが変わってるっていうのをちょっと一つ二つでも、教えていただけると嬉しいんですけど。
コンサルタントというと、お客様である企業様から答えや意見を求められることが多いです。しかし、コーチングを始めてからは、相手のニーズやお話をじっくりと聞き、対等な立場で接することを心がけています。その結果、相手がこちらに依存したり、上下関係が生まれたりするのではなく、むしろ非常に前向きになってくださるようになりました。
対話を通じてご自身の答えを見つけ、行動力が増していくように感じます。そのため、私は自身を単なるコンサルタントというより、「コーチ的コンサルタント」あるいは「コンサル的なコーチ」と呼ぶ方がしっくりくるかもしれません。そのような関わり方になったことで、仕事も順調に進んでいると感じています。
このアプローチは、研修においても同様です。私が一方的に教えたり、最近多いオンライン研修でウェビナーのように情報を発信したりするだけではありません。双方向性を重視し、グループワークやブレークアウトルームなどを積極的に取り入れています。その結果、参加者の皆様がより積極的に課題へ取り組み、ご自身で行動プランを作成して実践に移すケースが増えているように感じます。
原林:そうですか。やっぱりコーチングの要素っていうのがちら散りばめられることで、コンサルとしての関わりも、学びの場の作り方なんかも変わってくるんだなっていうことが、伺えました。ありがとうございます。
5-ACC資格を取ろうと思ったきっかけ
原林:そんな鈴木さんがですね、このACCを取ろうって思われたきっかけはどんなことですか?
ICF(国際コーチング連盟)の理念や倫理規定は、時代とともにその必要性や重要性が増していると以前から感じていました。
ヘルスコーチジャパンで学んだため、知識としては知っているつもりでおり、「それで十分だ」と考えていた時期もありました。しかし、自分の中での一つのけじめとして、資格をきちんと取得しようと決意しました。
規定に沿ったコーチであることを自覚することで、自信を持って倫理規定についても語れるようになると考えたのです。資格取得は、自分の中にあった「未完了」の課題を終わらせ、新たな区切りをつけるような感覚でした。
原林:未完了に区切りをつけたかったんですね。ACCCを取って、何かが変わったっていう感じはありますか?
資格を取得してからまだ1ヶ月ほどですので、正直なところ、目に見えるほどの大きな変化は感じていません。
しかし、自分の中で意識の変化はありました。以前は、倫理規定について「語れる」というよりは「知っている」という程度の認識で、積極的に他者へ話すことはありませんでした。資格取得後は、「私はこの規定を深く理解し、それに沿ってコーチングを行っている」という自覚が、自分の中で明確になりました。
これは誰かに話すことではありませんが、自分の中での一つのけじめとなり、規定への理解がより深まったように感じています。
原林:自覚とかね、意識づけとか、矜持みたいのが伝わってくる感じがしますね。
6-資格取得要件の100時間はどうやって達成したのか?
原林:これからACCを取ろうと思ってらっしゃる方々も気になるとこですけど、100時間、時間を積まなきゃいけないんですが、お仕事をなされながら鈴木さんはどうやってこの100時間を積んでこられましたか?
資格取得に必要な単位については、コーチ仲間との練習や、ヘルスコーチジャパンのプログラム内で取得しました。
実習時間に関しては、主に二つの方法で確保しました。一つ目は、コーチ仲間と開催している演習会や勉強会への参加です。
二つ目は、私の本業である研修講師の仕事です。幸いなことに、研修の一環として、企業の方々と1対1のコーチングやフォローアップを行う機会がありました。これらの機会があったおかげで、実践時間は比較的スムーズに確保できたと思います。
原林:なるほど。研修をなさったときにフォローアップという形でクライアントになっていただく、コーチングをさせていただくってことはありますよね。
はい、私自身も実践の場を確保しなければと考えていたため、研修後のフォローアップについては積極的に提案しました。
研修の参加者の方々には、「コーチングは、理論やスキルを学ぶだけでは身に付きません。必ず実践することが重要です」とその必要性をお伝えしました。その上で、1対1のフォローアップコーチングをご提案したのです。
料金も、通常の企業向け価格より少し利用しやすい設定にし、皆様に実践の機会を持っていただけるようお勧めしたところ、多くの企業でこの提案を受け入れていただくことができました。そのようにして、実践の機会を確保できたという経緯です。
原林:そうですか。企業でそういう研修のお仕事なんかなさってる方はこのやり方参考にしていただけそうですね。
はい、提案してみるのを駄目もとということで、提案してみるのはいいかなと思います。
原林:ありがとうございます。
100時間の実績セッションは、100時間のうち75時間が有料セッションでなければなりません。鈴木さんの場合は、本業の研修やコンサルティングと組み合わせて提案することで、無理なく達成されたようです。
人によっては、社内で許可をとり、社内コーチングで達成される方もいらっしゃいます。人事部への許可が必要ですが、給料をもらってやっているコーチングになるので、有料カウントができるのです。
ただし、上司が直属の部下に行うコーチングは、実績セッションとはみなされなくなっています。この理由は、上司部下の関係性の中で行うと、コーチングで最も重要な、Partner Withができなくなるからと思われます。
7-ICF Credentialing Exam対策としてやったこと
原林:ACC取得にはクレデンシャルエグザム試験がありますけれども、こちらは何かご苦労されたことなんかありましたか?
はい、試験の準備として、まず多くの方がされているように公式サイトの対策から始めました。公式ページに掲載されている10問の模擬試験や模擬質問を確認し、さらに解答の正当性を自分なりに確かめるため、倫理規定やコア・バリューを改めて読み直しました。そして、どの部分に該当する記述があるかを一つひとつチェックしていきました。
それに加えて、外部の学習ツールも利用しました。すでにご存じの方も多いと思いますが、ドイツのウェブサイト「Solution Academy」に無料の試験シミュレーターがあり、私もこれを活用して準備を進めました。
原林:このシミュレーターはあれですよね、最善と最悪を選ぶパターンですよね?
はい。
原林:なるほど。その後、試験の仕組みがちょっと変わりましたよね。実際に受けられたのは最善最悪を選ぶのではない、新しい形式の方だと伺いました。
はい、試験形式が変更されるというアナウンスがありましたね。以前、Solution Academyのシミュレーターを試した際、私は「最悪の選択肢」を選ぶ問題で間違いが多く、難しいと感じていました。
そのため、「最善の選択-肢を一つだけ選べばよい」という新形式への変更を知ったときは、こちらの方が自分には合っているだろうと考えました。資格の取得を先延ばしにしてしまっていたのですが、この変更を機に受験を決意したのです。
確か試験は昨年の後半に変わったと思いますので、その変更後に合わせて受験しようと計画を立てました。
原林:そういうことですね。実際に受験されるまでに、エントリーしてから日程変更なんかもされたっていうことをちらっと伺ってたので、その辺のご苦労があったかなと思って、さっき私どんなご苦労がと言ってしまったんですけど、その話聞いてもいいですか?
はい、私も試験内容の変更が発表され、先に受験した方から評判が良いと聞いてエントリーしました。しかし、申し込み後は仕事や母の介護などが重なり、予定していた日程での受験がどうしても難しくなってしまいました。そのため、何度も日程を変更することになったのです。大きな声では言えませんが、10回近く変更したと思います。
驚いたのは、その日程変更の手続きが非常にスムーズだったことです。特に何かを言われることもなく、確か試験の2日前までであれば、時間に関わらず夜中でもインターネット上で手続きが可能でした。申請をするとすぐに確認メールが届き、滞りなく変更が完了します。
何度も変更することに申し訳なさを感じつつも、この経験を通じて、仕事や様々な事情を抱える人にも広く受験の機会を与えてくれる組織なのだと実感しました。どんな人にもチャンスがあるのだと、よく分かりました。
原林:試験日の48時間以上前っていうことを守ってれば、何回でもそのリスケに応じてもらえるということなんですね。
私自身、10回近く日程変更を繰り返しましたが、その経験から、期限さえ守れば、本当に臨機応変に対応してくれる機関なのだと分かりました。
原林:その手続きは日本語でできるんですか?英語でなければ駄目なんですか?
ウェブページの最下部(ボトム)に言語の選択機能があります。そこで「日本語」を選択すれば、試験会場や試験日の選定画面なども含めて、すべて日本語で表示されました。
そのため、どなたでも簡単に手続きができると思います。
原林:見てくださる方に、きっと参考になると思います。
もう一つ、心配していたことがありました。何度も日程変更を繰り返していたため、申し訳なく思い、以前に連絡をいただいたことがあったICFの担当者の方へ、お詫びのメールをお送りしたのです。
すると、英語で非常に丁寧な返信がありました。内容は「ご安心ください。スケジュールは確保されていますので、そのまま会場で受験してください」といった、こちらを安心させてくれるもので、その親切な対応に大変驚きました。
原林:そうなんですね。なんかほっとしますね。そういうのを聞くとね。
以前は、ACC資格取得のときも、それよりももっと上級のPCC・MCC資格取得のときも、経験重視のICF Credential Examという試験を受ける必要がありました。
ところが、まだ100時間の実績しかもっていないACC新規資格申請者にとって、経験重視のICF Credential Examは難しすぎるという、世界中からの声があり、ICFはその声を受けて、まだ経験が浅いコーチ達も達成できる試験として、知識重視のACC Examを作りました。
2025/05/02以降は、ACC新規申請の場合は、全員がACC Examを受検する、ということに統一されています。
鈴木さんが受講された、コーチングスキル完全マスターL1コースには、ICF資格取得サポートのプロダクトがもれなくついているので、このようなICFの制度変更や、試験の変更などの最新情報を、常にキャッチすることができるようになっています。
この特典は、ヘルスコーチ・ジャパンだけが行っているもので、受講者から「英語申請でも迷わなかった」「わかりやすくて助かった」「仲間がいる安心感があった」という高評価を受けています。
8-ICF Credentialing Examの申込と申込後の流れ・試験会場の様子について
原林:当日は試験会場に行って受けられたんですよね?
そうです。
原林:会場での様子はどんな感じでしたか?
私が選んだ都内の会場は大規模な施設でした。そこではICFだけでなく、TOEICや英検、マイクロソフト社の各種認定資格など、様々な試験が同時に実施されており、多様な目的を持つ大勢の人が集まっていて、まずその光景に驚きました。
多くの方は事前に会場の下見をされるようですが、私は通勤経路の途中にあったため、特に下見はしませんでした。しかし、いざ行ってみると受付には長蛇の列ができていました。指定時間の15分ほど前に到着したにもかかわらず、手続きを終えたのは時間ぎりぎりでした。受付開始時間には列が階段まで続くほどの混雑ぶりで、その人の多さにも大変驚きました。
最終的に、その会場でICFの試験を受けていたのは4名ほどでした。受付に並んでいた大勢の人のことを思うと、その少なさはとても意外に感じました。
原林:時間に余裕を持って受付に入った方がよさそうですね。
そうですね。会場にもよりけりとは思いますが。
原林:実際試験が始まってからはどんな感じでしたか?
はい、会場では様々な試験の受験者が同じ部屋に案内され、席も混在していました。
会場にはそのような部屋がいくつかあるようですが、私が入った部屋は30席ほどの規模で、それぞれパソコンが設置されたブース形式で仕切られています。部屋の中はとても静かで、皆さんがそれぞれの試験に粛々と取り組んでいるという印象でした。
また、受験する試験が異なるためか、着席する時間や退出する時間は一人ひとり全く異なりました。しかし、周りを気にせず自分のペースを守り、落ち着いて取り組むことができれば、他の受験者の動きは気にならないと思います。
原林:そういう周りの状況もあり、この受けようとしているクレデンシャルエグザム自体は2部制?
はい、試験の途中で10分間の休憩が1回あります。前半が終わると画面にアナウンスが表示され、休憩を取るか、そのまま続けるかを選択する仕組みです。
私は気分転換のために休憩することにしました。休憩を選択すると、画面に10分間のカウントダウンタイマーが表示されます。休憩中はトイレなどで席を立つことも可能なのですが、再入室時の服装チェックなどの手続きが厳格で大変そうだと感じました。
そのため私は席を離れず、その場で立ち上がって背伸びをしたり、目を閉じて思考を整理したりして過ごしました。10分間は想像以上に長く感じられ、十分に心身を休めることができたと思います。
原林:外へは出ずにデスク周りで休憩を取られた感じだったんですね。
はい、そうです。
原林:ありがとうございます。
Examは、会場受験とオンライン受験の2つの方法から選べます。
会場は全国にあり、試験の運営は、ピアソンVUEというところがやっています。ここは、ICFの試験だけでなく、マイクロソフトやIBMなどの試験も行っているので、隣の席の人は、違う試験を受けているという状態になります。
これまでの合格者からの情報によると、高橋洋さんは、自宅でのオンライン受検で、結局当日になってつながらないということになり、会場受験に変更したという報告があります。
その後、野田茉里奈さんは、当団体初のオンライン受験をされました。
詳しくは、野田茉里奈さんの合格者インタビューをご覧下さい
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
会場は、そこそこでかなり状況が違いますが、試験開始直前にならないと入れない、ということは、複数の人が話しています。
石田真由さんは、周りの音が気になって集中できなかったので、会場備え付けの耳栓を使ったとのことでした。
試験は、ピアソンVUEというところが一括して請け負っているので、下記から詳しい情報を手に入れておいてください
9-ヘルスコーチ・ジャパンのプログラムの良かったところ
原林:さっき対策のお話もしてくださいましたけれども、ヘルスコーチジャパンのプログラムの中でACCを取ること全般についてこんなとこよかったよっていうのを聞かせてください。
やはり、コンピテンシー講座は非常に役立ちました。
コンピテンシーの規定を一人で読み解くのは大変な作業ですが、講座ではその内容について、クラスコーチや他の受講生の方々と直接対話をすることができます。また、ブレークアウトルームで仲間と情報交換をしたり、討議をしたりする時間もあり、こうした双方向の学びが理解を深める上でとても勉強になりました。
原林:やっぱり倫理規定とかコンピテンシーって、1人で頑張ろうと思ってもなかなか難しいところがありますよね。
はい。
原林:ヘルスコーチジャパンのコアコンピテンシーのクラスって話してみること、話を聞きながら自分たちでも話すことがすごくいいっていうふうにおっしゃいましたけど、特に印象に残ったことなんてもしあったら聞いてもいいですか?
はい、私自身、仕事でコーチングを実践しているため、特に倫理規定に関する討議は有益でした。例えば、「利益相反」や「自身のビジネスとの関連付け」といったテーマを扱ったブレークアウトルームでの討議は、自身の状況と重なる部分も多く、非常に身近な問題として捉えることができました。
倫理規定があるからこそ、コーチとしての姿勢、クライアントとの関わり方、そしてコーチングを依頼された企業様といった関係者との適切な関係性の築き方が明確になるのだと実感しました。また、「どのような場合に、どのような話し合いをすべきか」「契約に何を盛り込むべきか」といった実務的な事柄が、非常によく整理され、明確になったと感じています。
もちろん、講座で学んだ内容は試験にも役立ちました。学習したことで、無意識のうちに解答できた問題もあったように感じます。このように、複雑な規定や状況に応じた対応について頭の中を整理できたことが、何よりも大きな収穫だったと思います。
原林:ご自身のお仕事に引き付けて考えることができるっていうのは、すごく魅力的ですよね。ありがとうございます。
ヘルスコーチ・ジャパンには、コアコンピテンシーと倫理規定に関するスペシャリストが、2025年9月現在3名在籍(ICFジャパン認定CODE&CCアンバサダー)現在勉強中のコーチが2名在籍していて、いずれも、メンターコーチ、クラスコーチとして活躍しています。
なので、他のスクールのコースに通っている人が、わざわざ当団体のコアコンピテンシーと倫理規定の講座を単発受講しにいらっしゃるケースも多数見受けられます。
当団体のコースの質の高さが評価されている証であると、誇りに思っています
10-ACC資格を今後どのように活かしていきたいか?
原林:そんなふうにして未完了を完了させて、ACCを手にされた鈴木さんなんですけれども、これからどんなことにチャレンジしてみたいですか?
はい、今回の経験が、これから学習される方々の参考になれば嬉しいですし、心から応援しています。
私自身も、倫理規定を深く理解し、資格を取得したからこそ、プロフェッショナルとして適切なコーチングを提供できるのだと実感しています。この資格を基盤に、今後も様々なことに挑戦していきたいです。
そして将来的には、より広い視野で活動していきたいと考えています。日本国内、特に企業においては、まだICFの認知度が十分とは言えません。この価値ある情報をより多くの方に広め、情報共有なども含め、自身の仕事を通じて皆様のお役に立てるような関わり方ができれば、大変嬉しく思います。
原林:さっきお聞きした、その自覚と気概を持って、ぜひ広めていただければ、皆さん喜ばれるなと思いました。
ヘルスコーチ・ジャパンは、ICFが定める核となる能力水準(ICF Core Compitency Model)について、専門的に学んだ、ICFジャパンCODE&CCアンバサダーが3名もいます。まだ日本に10数名しかいない専門家が3名もいるので、ACC-Exam合格に欠かせない、コアコンピテンシーと倫理規定に関する勉強を深く行えるのです。
11-これから資格取得にチャレンジする人への応援メッセージ
原林:最後にこれからACCを取ろうと思って、今勉強してらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけれども、これからチャレンジする方への応援メッセージを一言いただけますか。
試験の内容や形式が変更されたことで、以前よりも受験しやすくなったと思います。そして、講座などで学んだことは、必ず結果に繋がります。
特に、ヘルスコーチ・ジャパンの講座は内容が非常に深く、そして何よりも「共に学ぶ仲間」の存在が非常に大きいと感じています。一人では考えがまとまらなかったり、曖昧だったりした点も、仲間と話し合い、情報交換をすることで明確になる、という経験が私には何度もありました。
仲間と切磋琢磨しながら努力を重ねれば、その分だけ必ず成果はついてきます。皆さんもぜひ、この挑戦を楽しんでいただきたいと思います。
原林:ありがとうございます。切磋琢磨できる仲間というところにまた戻ってきて、そんなコーチングの世界の良さだったり、これからの鈴木さんのご活躍もすごく楽しみなところで、今日のお話を聞かせていただきました。ではこれからも一緒に磨き合っていければと思っております。どうぞよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
原林:ありがとうございました。
12-プロフィール
鈴木輝子(すずきてるこ)

青山学院大学経営学部卒業後、KIKKOMANEU海外事業部でマネージャーとしてのキャリアを積む。帰国後、広告代理店にてプランナー&プロデユ-サ-業務に従事。その後、組織コンサルタントとプロコーチとして独立。
パーソナル(個人の強み・価値・自己基盤・キャリア向上)からビジネス分野のコーチとして「夢や目標を実現したい、問題や悩みを解決したい!解っているけど行動や実行へ移せない」と思うあなたのお話を聴いて、あなたの強みを発見し、今の自分から一歩進み出すお手伝いをしています。
Your dream comes true!
挑戦し続けるビジネスパーソンを応援し、働く人と組織の行動変容とその習慣化・定着化に全力を注いでいます。
<コーチングで私が大切にしている事>
1.あなたとの出会い
2.尊敬と信頼
3.共感と愛
<コーチングしている皆様からいただく声>
- 「不思議と昔からの友人のように話ができる」
- 「話を聴いてもらうと元気が出る」
- 「自分の気がつかない自分が発見できた」など等。
皆様の問題解決や成功が自分のこと以上に嬉しいです。
原林滋子(はらばやししげこ)

コーチングオフィスSmile-bloom代表
コーチ(パーソナルコーチ、メンターコーチ)
大学・専門学校非常勤講師
北海道札幌市在住
- 大学卒業後、自治体・金融機関のシステム開発に従事
- 大学付属実験施設での研究助手に転職
- 結婚後、在宅で資格試験の作問・校正、web開発に従事しながら非常勤講師となる
- 非常勤ゆえの「学生と短時間で信頼関係を築く」難しさに直面、子育てにも悩んでいたときにコーチングと出会う
- 2013年よりコーチとして活動、後進の育成にも携わる
【所有資格】
- 国際コーチング連盟(ICF)プロフェッショナル認定コーチ(PCC)
- NPO法人ヘルスコーチ・ジャパン認定 メンタルコーチ/ヘルスコーチ
- NPO法人日本優良セラピスト支援連盟認定アサーションアドバイザー
- 日本グリーフ専門士協会グリーフ専門士